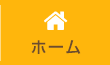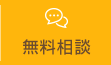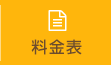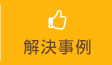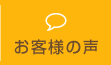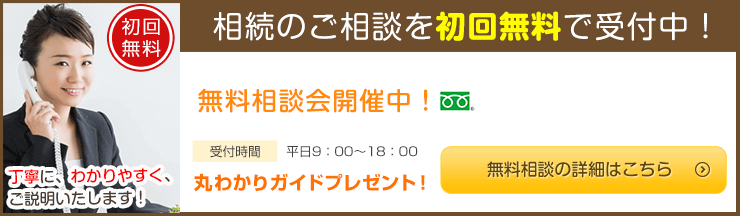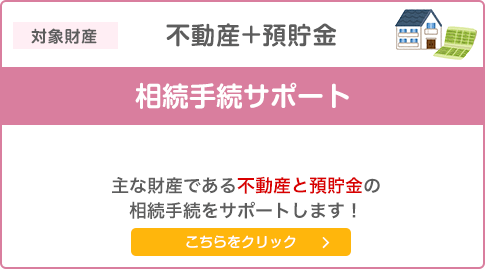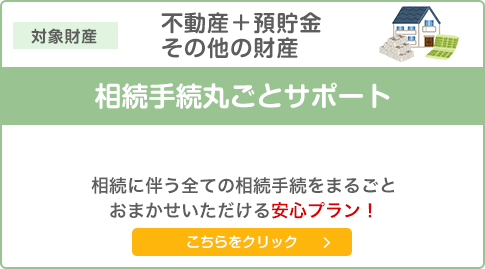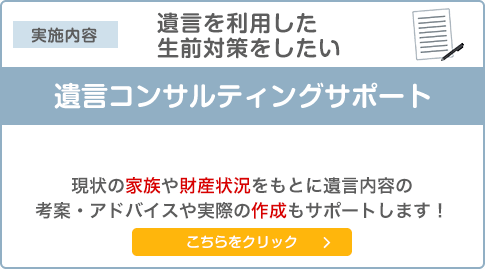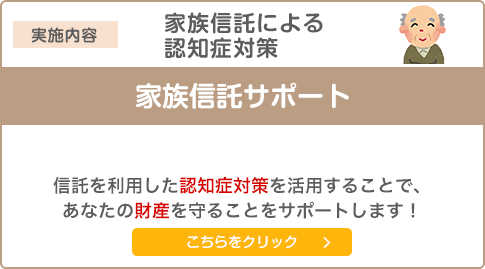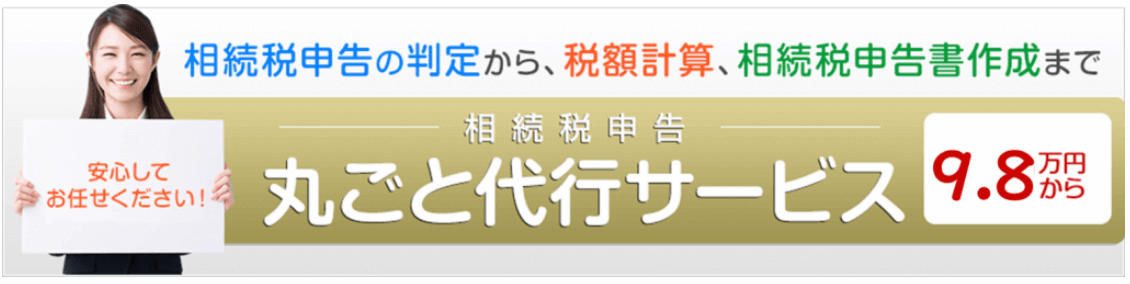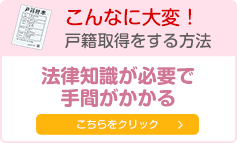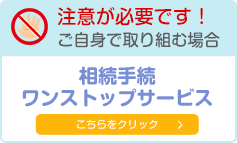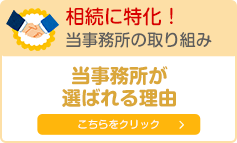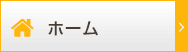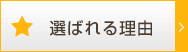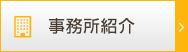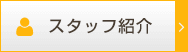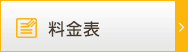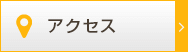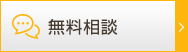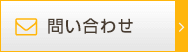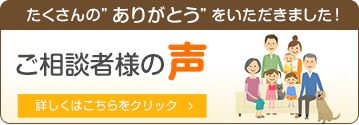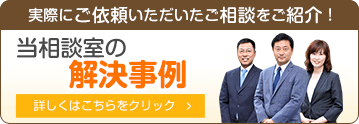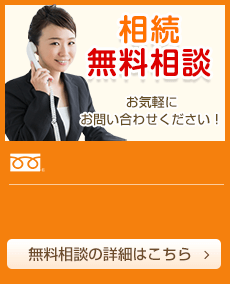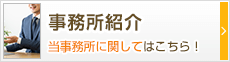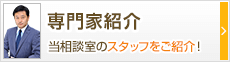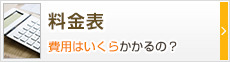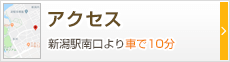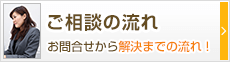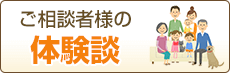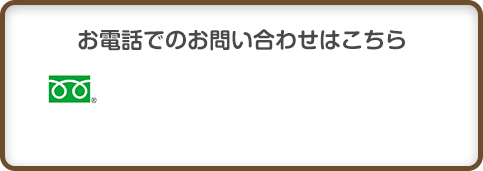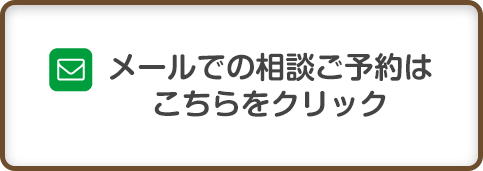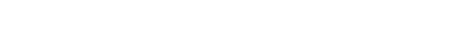代襲相続とは?制度のしくみを具体例を挙げてわかりやすく解説
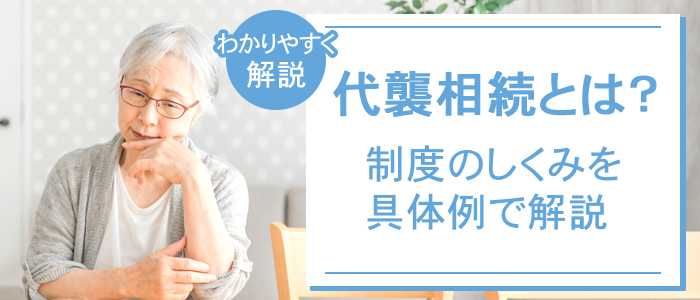
遺産を取得する権利は、相続が開始した時点の状況で判断することになります。
相続人が故人よりも先に亡くなっている場合、その人は相続権を失いますが、代わりに代襲相続人が遺産を取得する権利を引き継ぎます。
本記事では、代襲相続の制度を具体的なケースを用いて、わかりやすく解説します。
代襲相続とは
代襲相続は、被相続人(亡くなった人)が亡くなった時点において、本来相続人となる人が先に死亡していたときは、死亡した相続人の代わりに遺産を取得する権利を引き継ぐ制度です。
たとえば、被相続人の子が被相続人よりも先に死亡している場合、相続人の子(被相続人の孫)が代襲相続人として相続人の地位を承継します。
遺産分割協議は相続人全員が参加しなければなりませんので、代襲相続人も分割協議に加わることになります。
そのため相続開始時点で死亡している相続人がいるときは、相続手続きをスムーズに完了させるためにも、代襲相続人の把握は不可欠です。
民法で定められている法定相続人の範囲

相続人になる権利を有している人は、民法で定められており、法定相続人になることができる人には順位があります。
配偶者は必ず法定相続人になる
被相続人に配偶者がいる場合、配偶者は他の相続人に関係なく必ず相続人になります。
配偶者は法律上の婚姻関係がある人をいい、別居や離婚調停が行われている状況であっても、婚姻関係があれば相続人となります。
一方で、同居しているパートナーがいたとしても、婚姻届を出していない内縁の妻(夫)や、離婚した元配偶者は相続人にはなりません。
配偶者以外が法定相続人になるケース
被相続人の配偶者以外の親族に関しては、相続人になることができる順番(相続順位)が定められています。
同順位に複数人がいるときは全員相続人となりますが、相続順位の高い人がいる場合、低い順位の人は相続人になりません。
<相続順位>
| 第1順位 | 被相続人の子 |
|---|---|
| 第2順位 | 被相続人の父母(直系尊属) |
| 第3順位 | 被相続人の兄弟姉妹 |
なお、配偶者は他の相続人の有無に関係なく法定相続人になるため、配偶者と子がいる場合、配偶者と子が相続人となります。
第1順位:被相続人の子
相続順位が最も高いのは、被相続人の子です。
被相続人の子には、離婚した元配偶者との間に生まれた子や認知した非嫡出子、養子も含まれますので、相続人に該当する人は戸籍等で確認する必要があります。
第2順位:被相続人の父母
被相続人に子がいない場合、被相続人の父母が法定相続人になります。
(被相続人の配偶者の父母は相続人にはなりません。)
相続開始時点において父母がすでに亡くなっている場合、相続する権利は祖父母に移ります。
第3順位:被相続人の兄弟姉妹
相続開始時点で、被相続人の子や父母(祖父母)が不在の場合には、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。
被相続人が高齢だと兄弟姉妹が先に亡くなっているケースもありますが、そのような場合には、兄弟姉妹の子(甥姪)が代襲相続人として相続権を有することになります。
代襲相続の範囲
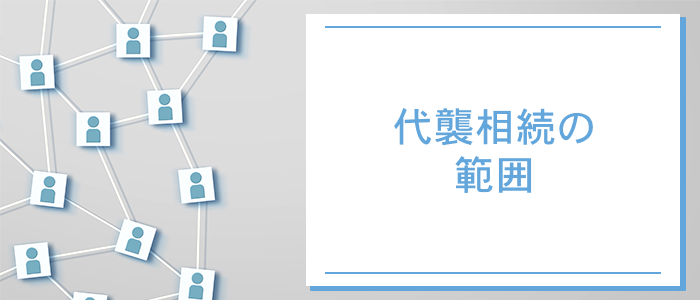
代襲相続が発生するケースのほとんどは、被相続人よりも先に本来の相続人が死亡している場合です。
相続開始前に子が死亡している場合
被相続人の子が相続開始前に亡くなっている場合、子の子(被相続人の孫)が代襲相続人となります。
被相続人の孫も先に亡くなっているときは、孫の子(被相続人の曾孫)が代襲相続人の地位を代襲(再代襲)します。
胎児は相続において「生まれたものとみなす」ため、相続人が亡くなった時点で生まれていない胎児についても、出生すれば代襲相続人として相続人の地位を引き継ぐことが可能です。
(死産の場合は、胎児の相続はなかったものとされます。)
被相続人に養子がいる場合、養子縁組したタイミングで代襲相続する権利の有無が決まります。
養子縁組前に生まれた養子の子は代襲相続する権利はありませんが、養子縁組後に生まれた養子の子は代襲相続する権利を有しますので、養子が相続開始前に亡くなっているときは、養子縁組した時期を必ず確認してください。
法定相続人の兄弟姉妹が先に死亡している場合
法定相続人である兄弟姉妹が相続開始前に死亡している場合、兄弟姉妹の子(被相続人の甥姪)が代襲相続人となります。
子の代襲相続とは違い、兄弟姉妹の再代襲は認められていないため、相続開始前に兄弟姉妹および甥姪が死亡していたとしても、甥姪の子は相続人の地位を引き継ぐことはできません。
法定相続人の死亡以外で代襲相続が発生するパターン
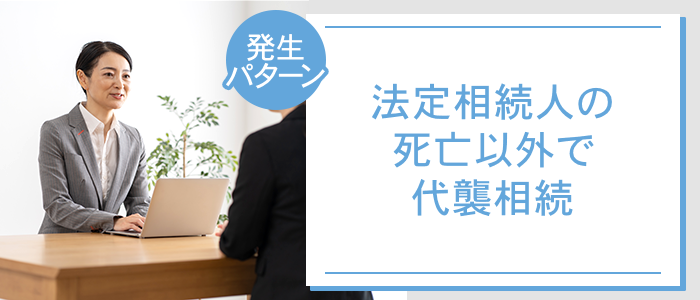
法定相続人の死亡以外で代襲相続が発生するパターンとしては、「相続欠格」と「相続廃除」があります。
相続欠格
相続欠格とは、相続人が次の犯罪行為や不正をした場合に、相続権が剥奪されることをいいます。
相続人が以下のケースに当てはまる場合、被相続人の意思に関係なく相続欠格は適用されます。
- ・被相続人や先順位もしくは同順位の相続人を死亡させたり、命を脅かすような行為をしたりした
- ・被相続人に対する脅迫や詐欺により、遺言書の内容を自分が有利になるよう撤回、変更させた
相続廃除
相続廃除とは、相続人が次の行為をした場合に、相続権が剥奪されることをいいます。
相続欠格とは違い、相続廃除は被相続人が生前に自分で家庭裁判所に申し立て、または遺言書で行うことで認められる制度です。
- ・被相続人に対して虐待や重大な侮辱行為をした
- ・相続人に著しい非行があった
相続放棄が行われた場合に代襲相続は発生しない
代襲相続は法定相続人の死亡により行われるのが一般的ですが、「相続欠格」や「相続廃除」があった際にも発生する可能性があります。
しかし、相続の権利を自ら放棄する「相続放棄」については、相続開始当初から相続人でなかったとみなされるものですので、相続放棄をした相続人の子や孫に代襲相続する権利はありません。
代襲相続の場合、相続割合はどうなる?
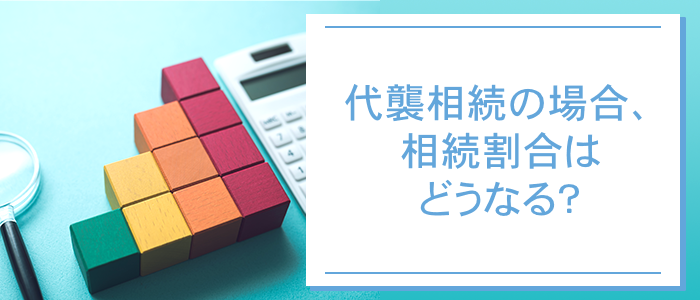
代襲相続では代襲相続する人(代襲相続人)が、自分の親が相続するはずであった相続分を引き継ぎます。
代襲相続人が複数人いる場合は、引き継いだ相続分を均等に割ることになりますので、代襲相続人以外の相続人の相続割合は同じです。
代襲相続人が「孫」の場合
本来の相続人であった被相続人の子が、被相続人よりも先に亡くなっている場合、子の子(孫)が子の地位を引き継ぎます。
法定相続人が配偶者と子のケースの相続割合は、配偶者と子が各1/2です。
子が相続開始前に死亡し、孫2人が代襲相続人となったときは、孫は子の相続割合1/2を2人で引き継ぐことになりますので、相続割合は配偶者1/2、孫は各1/4となります。
代襲相続人が「甥姪」の場合
法定相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合、相続割合は配偶者3/4、兄弟姉妹1/4です。
兄弟姉妹が相続開始前に死亡しており、兄弟姉妹の子(甥姪)が2人いる場合、甥姪の相続割合は各1/8です。
代襲相続が発生した際の注意点
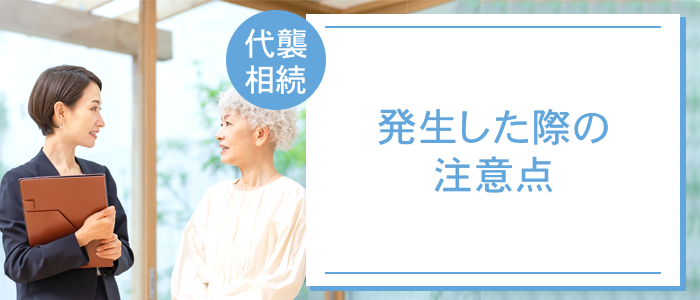
代襲相続が発生する場合、通常の相続とは異なる部分が出てきますので、相続関係の手続きを行う際は気を付けてください。
相続人の数が増えることがある
代襲相続人が複数いる場合には、法定相続人の数が増えます。
法定相続人の数が増えると遺産分割協議の参加者が多くなるだけでなく、相続税の計算にも影響してきます。
相続税の基礎控除額や死亡保険金などの非課税限度額は、法定相続人の数に応じて増減するのが特徴です。
たとえば、相続税の基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の計算式で求めることとなっており、代襲相続が発生したことで法定相続人が1人増えれば、本来の相続人が健在だったときより基礎控除額は600万円多くなります。
代襲相続人の遺留分の扱い
遺留分とは、一定の相続人に最低限保障されている遺産の取り分のことです。
遺言に「長男に全財産を遺す」「愛人に財産を贈る」などと書かれていたとしても、一定の範囲の相続人は請求することで必ず一定の財産が取得できます。
一定の相続人とは、被相続人の配偶者と、直系卑属(子・孫・曾孫)と直系尊属(父母・祖父母・曾祖父母)をいい、兄弟姉妹は含まれません。
代襲相続は、相続人の地位をそのまま引き継ぐものですので、遺留分を請求できる権利がある地位を引き継いだ代襲相続人は、遺留分を請求することが可能です。
しかし兄弟姉妹については遺留分を求める権利がないため、甥姪が代襲相続人になったとしても遺留分はありません。
戸籍謄本などの収集すべき書類の量が増える
相続手続きにおいては、相続人の数などを確認するために戸籍謄本を取得しなければなりません。
相続人が被相続人よりも先に亡くなっている場合、誰が代襲相続人となるかを明らかにするために、被代襲者(本来相続するはずだった相続人)の出生から死亡までの戸籍謄本や、代襲相続人が被代襲者の子であることを確認するための戸籍謄本が必要になります。
法定相続人が兄弟姉妹の場合、甥姪の数によっては取得すべき戸籍謄本の量も膨大になるため、代襲相続人がいるときの相続手続きは、書類を準備するだけでも手間がかかります。
代襲相続で発生しやすいトラブル

代襲相続は、孫や甥姪、場合によっては曾孫など、世代の違う人たちが相続人になるためトラブルになりやすい傾向があります。
相続人同士が疎遠になっているので話し合いが進まない
相続人が配偶者と子以外の場合、相続人間の意思疎通が難しい場合があります。
相続人が子のみであっても、被相続人の前妻の子がいる場合や、その子が先に亡くなっていることで子の子(孫)が代襲相続人になる場合、遺産分割協議の場で初めて対面することになるケースも珍しくありません。
そのような状況下では話し合いが難航しやすいのはもちろんのこと、話し合いの場を設けるのにも時間を要します。
相続手続きには期限が定められているものもありますので、状況次第では早めに専門家へ依頼することを検討してください。
代襲相続人の知識不足で不利益を被る
自分が代襲相続人であることを把握しておらず、上の世代の相続人同士で勝手に遺産分割協議を終わらせてしまうケースがあります。
代襲相続人だと認識していないと、相続することができた遺産を他の相続人に取得され、知らない間に不利益を被る可能性もあります。
そのため、現時点で親が亡くなっている方につきましては、相続人の立場を引き継ぐことを理解しておきましょう。
代襲相続・相続税の相談は新潟相続相談室へ
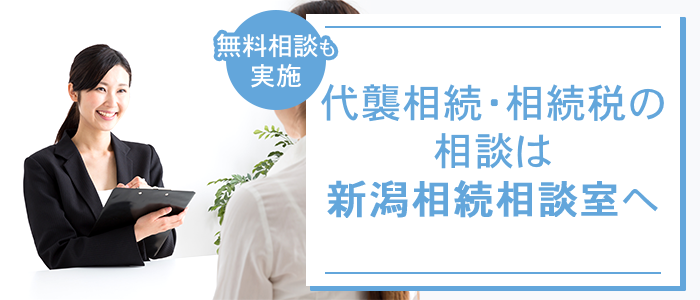
代襲相続人がいる相続は、通常の相続よりもトラブルが起こりやすい傾向にあります。
感情論が強くなってしまうと話し合いがまとまらず、相続手続きも長引いてしまいますので、本来の相続人が先に亡くなっているときは、生前中に対策を講じることも一つの手段です。
相続は専門用語や専門知識を必要とする場面が多く、相続人だけで対策しようとしても、失敗してしまう可能性もあることから、相続関係のお悩みにつきましては専門家にご相談することをオススメします。
新潟相談室は、新潟市を中心に新潟県全域の相続に関するサポートをしている、相続専門の事務所です。
相続問題に強い弁護士や司法書士とも連携し、代襲相続や一般的な相続で起こるトラブルにワンストップで対応します。
また、当事務所では無料相談も実施していますので、相続に関する不安が少しでもございましたら、お気軽にご相談ください。