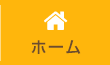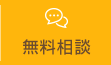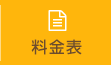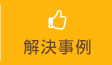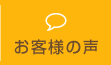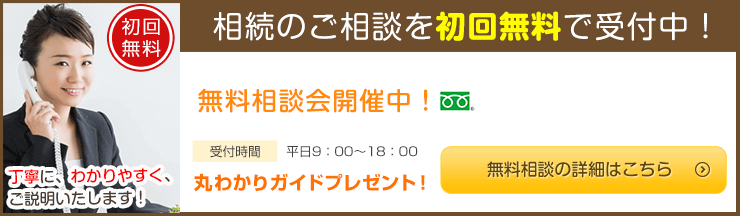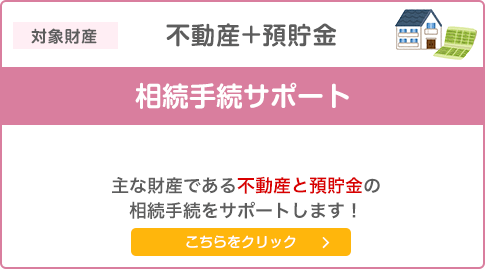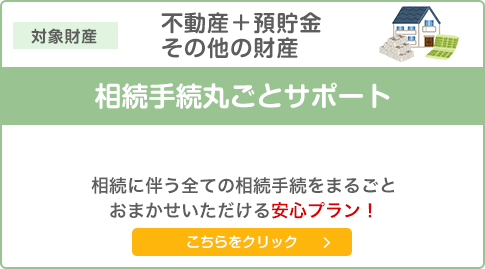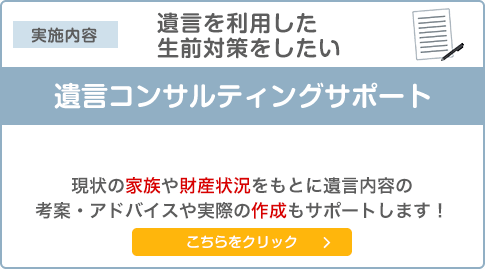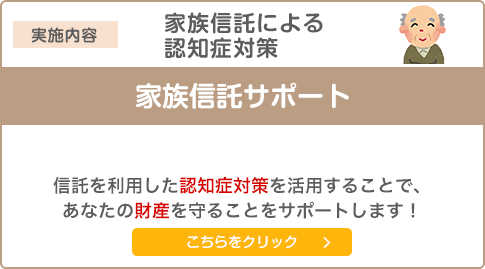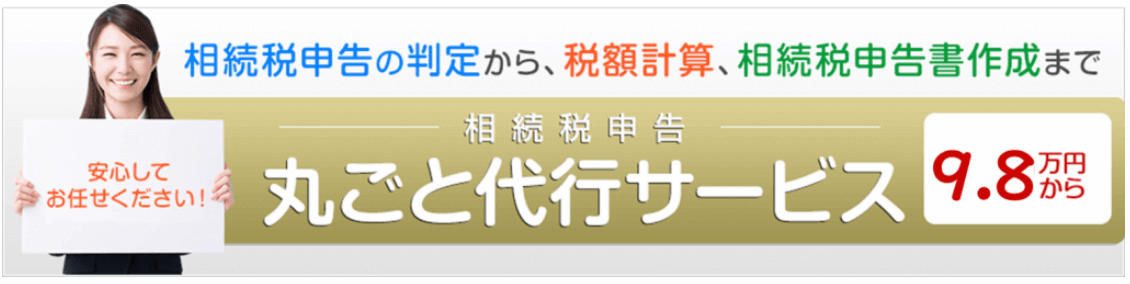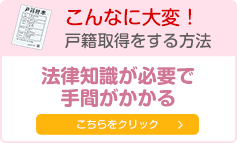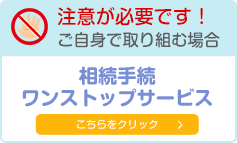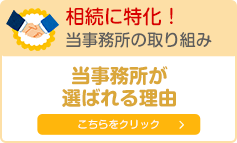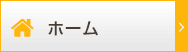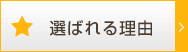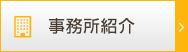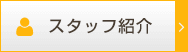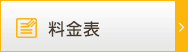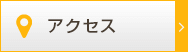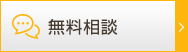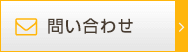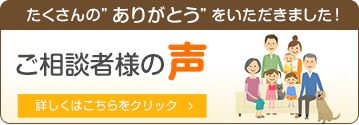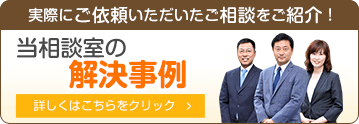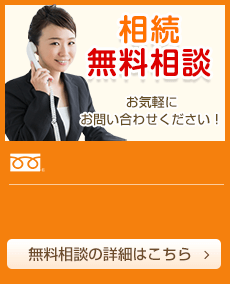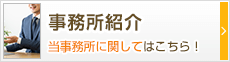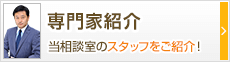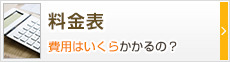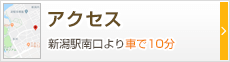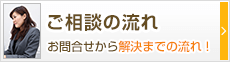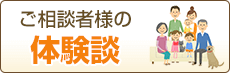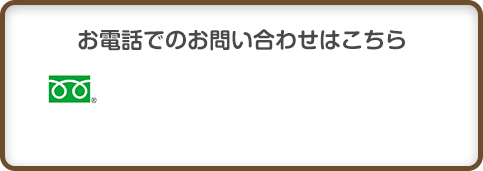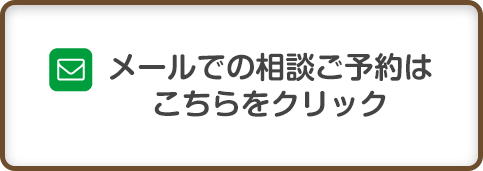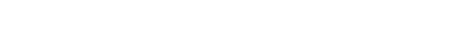相続登記の義務化。制度の概要と改正による影響を専門家が解説
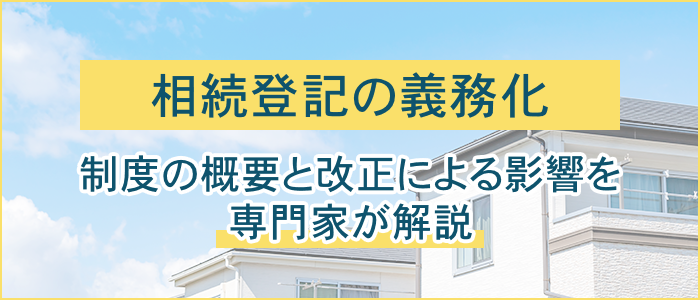
不動産を相続した場合、法務局で登記の名義変更手続きをしなければなりませんが、令和6年(2023年)4月1日から相続登記手続きは義務化されます。
一定の期間内に相続登記を行わなかった場合、罰則を受ける可能性もありますので注意しなければなりません。
本記事では、相続登記義務の概要および、法律の改正前後に相続登記手続きを行う際の注意点について解説します。
相続登記が義務化される経緯
不動産を相続した際の登記名義の変更は、今まで義務ではありませんでした。
しかし、相続登記が行われない事例が多発している等の理由から、令和6年(2023年)4月1日から相続登記は義務となります。
相続登記が義務化される最大の要因は、名義変更されずに放棄されている土地・建物が日本各地に点在していることが社会問題になっているからです。
不動産登記は、不動産の所有者を明らかにすることで円滑に取引等を行えるようにする目的があり、所有者と登記上の名義人が一致していなければ不動産を売却することはできません。
一方で、相続登記には労力と費用がかかりますし、価値の低い土地は売却するのが難しいことから、名義変更しないことによるデメリットが少ないため、相続で土地を取得しても登記手続きを行わない事例が増加しています。
所有者不明の土地は管理されずに放置されますし、相続登記がされないまま次の相続が発生してしまうと、相続登記を行うのがより困難になります。
そのような状況を解決するために、国は所有者不明の不動産を無くす手段の一つとして、相続登記を義務化することを決定しました。
不動産の名義変更(相続登記)が必要な理由について詳しくはこちら>>
「不動産の相続手続きが必要な理由」
登記上の20%は所有者不明の土地
国土交通省では、所有者不明の土地を「不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない、又は判明しても連絡がつかない土地」と定義しています。
平成29年の法務省が行った調査によると、不動産登記簿における相続登記がされていない土地(最後の登記から50年以上経過)の割合は、大都市で約6.6%、中都市・中山間地域で約26.6%との結果が出ています。
また、地籍調査における土地所有者等に関する調査(平成30年版土地白書114頁参照)では、不動産登記簿のみでは所有者の所在が確認できない土地の割合は約20.1%と、多くの不動産が登記上で所有者が確認できない状態です。
土地を所有者不明のまま放置するデメリット
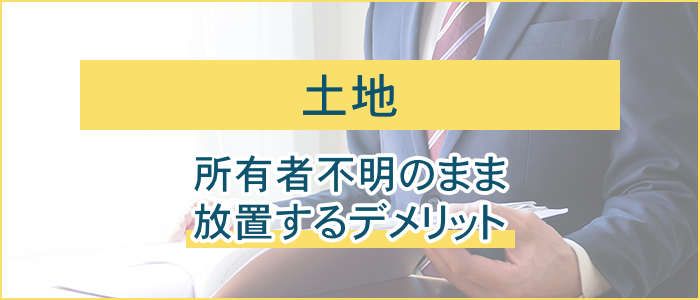
所有者不明の土地を放置する主なデメリットは、次の2点です。
所有者を探し出すのに手間がかかる
相続登記が行われないことで所有者不明になっている土地は、登記簿上の所有者の存在を確認しなければなりません。
所有者が死亡している場合、所有者の子などの相続人が話し合いを行い、誰が不動産を引き継ぐのかを決めます。
相続人が配偶者と子であれば、話し合いも比較的まとまりやすいですが、相続人がすでに亡くなっているときは、相続人の子(被相続人の孫)を遺産分割協議に参加させることになります。
血縁関係が遠くなるほど親戚付き合いしなくなるので、連絡を取るのも難しく、協議の場を設けること自体が大変です。
有効活用されない土地が増加する
利用価値の高い土地であれば、相続人は時間と労力をかけて相続登記を行うメリットがあります。
しかし、相続登記を完了させないと売ることはできないため、第三者が土地を購入したいとの申し出があったとしても、売却に応じることはできません。
売却のタイミングを逃せば、いつ売却できるかわかりませんので、使い道のない土地が残り続けることになります。
相続登記の法律改正に伴う変更点
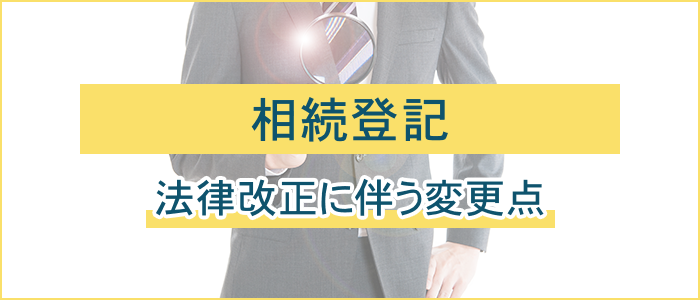
相続登記に関する法律が改正されたことで相続登記の義務化だけでなく、相続手続きに関する事項も変更されている部分がありますので併せてご紹介します。
相続登記の義務は3年以内
不動産の名義変更登記は、相続の開始および、所有権を取得したことを知った日から3年以内にしなければなりません。
相続登記の義務は、遺産分割協議や遺言、遺贈などにより不動産を取得する人に対して課されます。
相続登記の罰則規定の創設
相続登記義務化することで問題点として指摘されているのは、罰則規定の創設です。
相続登記を正当な理由がないにもかかわらず手続きしなかった場合、10万円以下の過料が科される可能性があるので注意してください。
- ・相続登記が放置されたことで相続人が極めて多数となり、戸籍謄本等の必要な資料の収集や、相続人の把握に多くの時間を要する
- ・遺言の有効性や遺産の範囲等が争われている
- ・申請義務を負う相続人自身に重病等の事情がある
相続人申告登記制度の創設
相続人申告登記制度は、申請義務を履行したものとみなす制度です。
相続人間の遺産分割がまとまっていない場合、期限までに相続登記を行うことできませんが、相続人であることを相続人申告登記制度による手続きを行えば、相続登記義務を履行したとみなされます。
ただし、相続人申告登記制度にも手続き期限があり、所有権の登記名義人について相続が開始した旨と、自らがその相続人である旨を申請義務の履行期間内(3年以内)に行う必要があります。
不動産の名義変更の手続きについて詳しくはこちら>>
「不動産の名義変更の手続き」
相続登記手続きの一部の簡素化
従来の相続手続きは、相続人全員が協力して手続きする必要がありました。
しかし今回の法律改正により、相続登記は不動産を取得した者が単独で申請することができるようになるなど、手続きの一部が簡略・簡素化されます。
相続登記手続きは義務化前でもやらなければならない理由
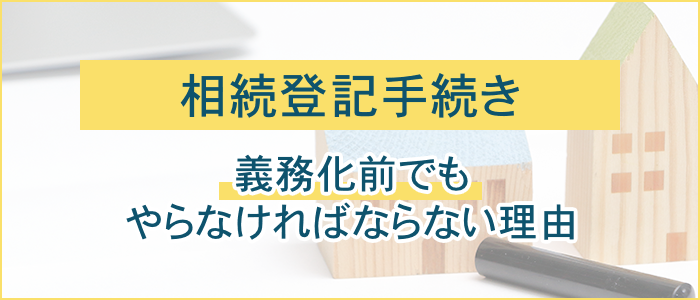
相続登記の義務化は令和6年(2024年)4月からですが、義務化前でも相続が発生しましたら、相続登記手続きは早めに行ってください。
不動産には管理義務がある
不動産は所有者が自由に使用処分することが認められている一方で、管理義務も発生します。
そのため早めに不動産を相続する人を決定し、新たな所有者が不動産を管理する体制を整えなければいけません。
空き家となっている相続財産が放置されていると、老朽化による倒壊等のリスクが高まりますし、周囲に被害が生じた場合には賠償問題に発展する可能性もあるのでご注意ください。
不動産を売却できない可能性がある
不動産は故人の名義で不動産を売却することはできませんので、相続登記は不可欠です。
不動産の売買は相手がいる話ですので、購入の申し出があったタイミングで売ることができなければ、不動産を処分するのが難しくなります。
遺産分割協議を先延ばしにするほど合意形成が難しくなる
相続の話し合いを先延ばしにすると、相続人が増え、遺産分割協議が成立しにくくなります。
相続人が全員存命であれば、話し合いを行うために集まることもそれほど難しい話ではありません。
しかし、何世代にもわたって相続登記が放置されている場合、相続人が数十人にものぼり、登記手続きにかなりの時間と労力が必要となることがあります。
相続人の中に未成年者・行方不明者・海外在住者・認知症者がいる場合、相続登記手続きの労力は一段と上がりますので、相続未登記不動産の存在に気がついた時点で早期に手続きしてください。
必要書類を揃えるのに時間がかかる
相続が発生した場合、被相続人の保有財産を引き継ぐ人を決めなければなりません。
預貯金や株式などの相続財産は解約等の手続きが必要となりますが、手続きには相続登記と同様、遺産分割協議書や戸籍謄本が必要です。
戸籍謄本等の必要部数をあらかじめ把握しておけば、戸籍謄本等を請求する手続きは1度で済むため、書類を集める手間を最小限に留めることができます。
一方で、相続登記手続きだけが遅くなった際は、戸籍謄本等を個別で集めなければなりませんし、先に亡くなっている相続人がいる場合、追加で用意すべき書類が増えてしまいます。
戸籍収集はこんなに大変な作業です!>>
https://niigata-isansouzoku.com/knowledge/page5/
親が所有している土地が相続未登記不動産であった場合
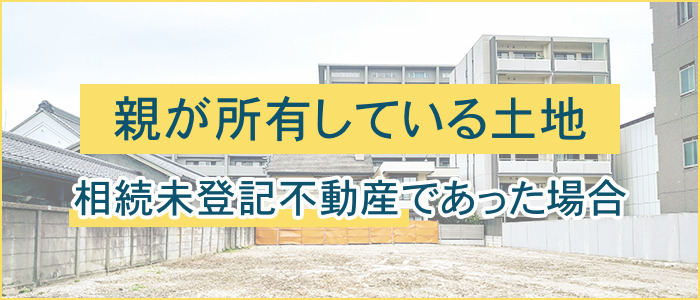
親の相続が発生したことで未登記となっている不動産は、気がついた時点でできるだけ早く対応することが得策です。
故人の所有不動産をすべて把握する
親が保有する土地が相続登記未登記不動産であることが分かった場合には、速やかに正しい所有者を登記簿に登録しましょう。
相続が発生しましたら、亡くなった人の全財産を漏れることなく把握してください。
相続登記をせずに所有者を明らかにしていないと、土地を使用処分できませんし、相続登記義務化後はペナルティの対象となります。
不動産登記の申請先は管轄法務局
不動産の名義変更は、不動産の所在地を管轄する法務局で行います。
相続登記の場合には、被相続人の戸籍謄本や住民票、固定資産評価証明書などの必要書類を申請書と一緒に提出することになります。
申請は法務局窓口以外に、郵送やオンラインで行うことが可能です。
一般的には窓口で申請することが多く、郵送申請は必要書類が漏れていると申請が受理されません。
オンライン申請については、事前に電子証明書等を用意するなど専門知識が必要となりますので、状況によっては専門家に依頼することも選択肢です。
申請時に登録免許税を納める
不動産の登記手続きをする場合には、対象不動産の固定資産評価額に一定の税率を乗じた額を登録免許税として納めることになります。
登録免許税は相続や贈与、売買などの登記手続きを行う原因によって適用税率が異なり、相続登記で適用される税率は0.4%です。
不動産登記に関する手続きは今のうちから対策すべき
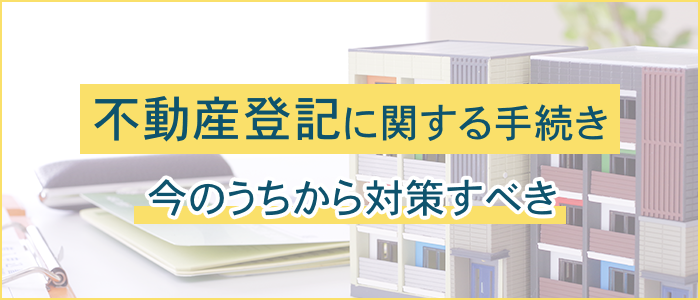
相続登記は専門家に依頼しなくても、相続人自身が手続きすることも可能です。
ただ法務局の窓口は日中にしか空いていませんし、不動産の数だけ登記手続きをしなければなりません。
相続人が多いケースにおいては、戸籍謄本など用意すべき書類を集めるのにも苦労し、何代にも渡って相続登記をしてない不動産の名義を変えるのには多大な時間と労力を要します。
コストを抑えるために相続人だけで手続きしようと頑張っても、何度もやり直しすることになれば費用対効果が悪いので、相続登記手続きは専門家である司法書士に依頼することもご検討ください。
相続手続きに強い専門家が無料相談対応いたします!
当事務所は、相続の累計相談実績1,000件以上と豊富な相談実績があります。
相続手続きはもちろんのこと、遺言書作成など相続に関わるご相談につきましては当事務所にお任せください。
現在、当事務所では相続の無料相談を行っております。
相続の専門家が親切丁寧に対応させていただきますので、下記の電話番号にお問い合わせください。
料金についてはこちら>>
https://niigata-isansouzoku.com/fee/
事務所紹介についてはこちら>>
https://niigata-isansouzoku.com/office/
無料相談についてはこちら>>
https://niigata-isansouzoku.com/flow/
相続手続丸ごとサポート(対象財産:不動産+預金+その他の財産)
相続人調査(戸籍収集)や遺産分割協議書の作成、預金口座や不動産の名義変更など、あらゆる相続手続きをまとめて代行いたします。
相続財産に不動産や、預貯金等の複数の財産がある相続人の方には、「相続手続丸ごとサポート(対象財産:不動産+預金+その他の財産)」がオススメです。
<相続手続丸ごとサポート(対象財産:不動産+預金+その他の財産)>
| 相続財産の価額 | 報酬額 | (参考) 金融機関 |
|---|---|---|
| 200万円以下 | 165,000円 | 100万円 |
| 200万円超 ~500万円以下 |
220,000円 | 100万円 |
| 500万円超 ~5,000万円以下 |
220,000円 ~814,000円 |
価格の1.62% |
| 5,000万円超 ~1億円以下 |
814,000円 ~1,364,000円 |
価格の1.08 ~0.864% |
| 1億円超 ~3億円以下 |
1,364,000円 ~2,904,000円 |
価格の1.08 ~0.864% |
| 3億円超 | 2,904,000円~ | 価格の0.648 ~0.324% |
相続手続丸ごとサポートについて詳しくはこちら>>
https://niigata-isansouzoku.com/zaisan/page1/